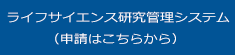![]()
トップ > よくある質問
よくある質問 FAQ
Q1:申請対象にあたるかの判断基準はありますか。
A1:「人を対象とする研究」のうち,研究対象者に対し、特に倫理的配慮が必要な研究のみが倫理審査の対象となりますが、その該当の有無は「倫理審査要否チェック」により研究責任者に判断いただきます。審査要否の判断やチェックリストは「人を対象とする研究」ページ>「倫理審査要否の判断について」をご参照ください。
Q2:倫理審査にはどのくらい時間かかりますか。
A2:通常審査の場合は申請書提出締切日から委員会承認・学長許可まで,1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。委員会開催日・申請書提出締切日をご確認のうえ,遅くとも実験や調査を開始したい月の2ヶ月前の締切日に間に合うように申請してください。また、迅速審査の場合は2~3週間程度かかります。なお、迅速審査対応の可否は申請内容で判断いたします。
Q3:東工大で研修会を受講していなくても申請することは可能ですか。
A3:本学の研究責任者および研究担当者は、東工大の研修会を必ず受講してください(【学内限定】倫理研修の受講)。eL CoreやeAprinの同様の研修では代用できませんので、ご理解のほどお願いいたします。学外の研究担当者がその所属機関で研修会を受講済の場合は、「所属機関で受講」と申告してください。そうでない場合は、東工大の研修を受講していただくことも可能ですので、委員会事務局にお問い合わせください。
Q4:特任教授や特定教授等は、研究責任者になれますか。
A4:本学が本務である特任教授等は、研究責任者になれますが、本学が本務でない特定教授等はなれません。
Q5:侵襲と介入の違いを教えてください。
A5:倫理指針における定義は以下をご参照ください。
侵 襲:研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。侵襲のうち、研究対象者の身体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいものを「軽微な侵襲」という。なお、fMRIは軽微な侵襲にあたります。
介 入:研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因(健康の保持増進につながる行動及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。)の有無又は程度を制御する行為(通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。)をいう。
Q6:研究対象者に未成年が含まれる場合の手続きを教えてください。
A6:子どもまたは、成年でインフォームドコンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される者を研究対象にするときは、代諾者(保護者や成年後見人)の同意が必要になるので、代諾者向けの説明書をシステム上で作成し、別添で①本人向けの説明書(様式10-1)、②代諾者および本人向けの同意書(様式11)、③募集要項(様式10-2)をアップロードしてください。
Q7:研究対象者に患者が含まれる場合は、どのような手続きが必要でしょうか。
A7:病歴や診療データは要配慮個人情報にあたります。患者を対象とする場合は、共同研究を行う医師の所属・氏名が必要になりますので申請書にご記載ください。
Q8:学生の研究参加に対する任意性が担保されていると判断するための条件とは何ですか。
A8: ・授業の成績と研究は無関係で、研究の参加・不参加が成績や研究室内での活動に影響することはないことを説明する必要があります。
・授業時間内で研究内容の説明や参加者の募集をしないようにしてください。(支障がなければ、成績発表後に研究を実施する方が良いです。)
・一度研究に参加しても、途中で参加を取り消したくなった時には、いつでも参加を取り消すことができることを説明してください。
・侵襲を伴わない研究の場合には口頭IC取得でも可能です。ただし、個別に学生に依頼することは、教員からの依頼を断りづらいと感じる学生が多くいることを考えて、参加を強制することがないように留意してください。Slack、掲示板(Science Tokyo LMSの研究目的利用は不可)などで募集し、参加希望者とのやり取りを保存しておくと自発的参加であることの記録を残すことができるので推奨しています。
・参加人数を増やすには、商用のアンケート請負会社を利用することも検討ください。
Q9:WEBアンケートを実施する場合は、同意・同意撤回をどのように受ければよいでしょうか。
A9:WEBアンケートの場合も通常と同じく募集条件を示して(募集要項)、WEBページにアクセスしてもらい、アンケートの目的などを説明(説明書)したうえで、参加への同意を取得する(同意書)ことに変わりはありません。ただし、無記名のアンケートであれば、同意書は書面(紙)ではなく、電子的方法(オンライン)で取得しても構いません。WEBページに掲示した説明書と同意書の内容を読んでもらったあとに、「同意してアンケートに進む」などのボタンを押下してもらうことで、同意を取得したとみなすことができます。
なお、相手の顔が見えないWEBアンケートの場合、未成年者に調査を行うのはなるべく避けてください。成人のみを対象とすることを募集要項で明確に謳ったうえで、同意取得の際に「成人であること」を確認条件に加えることを推奨します。ただし、保護者から適切に同意を取得していることを確認する手段がある場合には、これに限りません。
また、無記名アンケートの場合は、回答を全て完了した後に、同意を撤回して収集済みのデータの破棄を行うことは困難です(どれが誰のデータなのか特定できないため)。回答を始める前もしくは回答中にしか事実上同意撤回できないのが通例です。
Q10:研究対象者からの相談等への対応はどのように行えばよいでしょうか。
A10:原則として、研究責任者が対応することとしてください。研究に関する問い合わせ先は、研究責任者もしくは研究室の電話番号・メールアドレスとしてください。なお、個人の携帯番号は(研究者自身の個人情報を守るという意味でも)用いないでください。
Q11:研究の結果、研究対象者の健康や遺伝的特徴について重要な知見が得られた場合は、本人に通知する必要がありますか。
A11:そういった研究結果をどのように取り扱うかを検討の上、申請書および説明書に記載してください。なお、それが偶発的に得られたものであって、それを本人に通知する場合には、確定診断ではない(医療機関の受診を勧める)ことを併せて明記してください。
Q12:個人情報、一次情報、二次情報とは何を指すのでしょうか。
A12:本学では、実験・調査研究におけるデータを以下のとおり区分しております。
個人情報:個人の属性
一次情報:実験・調査で得られた情報
二次情報:研究のために個人情報を削除または符号化し、それのみでは個人を特定できなくなっている情報
Q13:①個人情報について、どのようなものがあるのか具体的な例を教えてください。また、②個人識別符号や③要配慮個人情報とはどのようなものでしょうか。
A13:①個人情報とは、氏名、性別、生年月日、連絡先などだけでなく、顔写真・映像(録画)・音声(録音)も含まれます。
(例)
・名前と紐づいていない、インタビューの録音・録画
・個人を判別できる防犯カメラの映像
・歩容(歩き方や腕の振りなど)の写った動画
②個人識別符号とは、番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたものを「個人識別符号」といい、個人識別符号が含まれる情報は個人情報となります。
(例)
・ゲノム情報、手指の静脈、顔認証データ、指紋、虹彩、声紋、歩行の態様、掌紋などのデータ
・サービス利用や書類において利用者ごとに割り振られる符号で、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバー、保険者番号など
③要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。要配慮個人情報の漏洩は法律で報告義務があります。
(例)
・本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実
・身体障害・知的障害・精神障害などの障害があること、医師等により行われた健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報
・本人を被疑者又は被告人として逮捕等の刑事事件に関する手続が行われたこと、非行・保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたことの記述
下表にそれらの例を示しています。詳細は個人情報保護に関する法律・ガイドラインをご確認ください。
| 個人情報 | 個人識別符号 | 要配慮個人情報 | |
|---|---|---|---|
| 氏名・生年月日 | 〇 | ||
| 写真・映像 | 〇 | ||
| 音声 | ○ | ||
| 免許証番号 | 〇 | 〇 | |
| 旅券番号 | 〇 | 〇 | |
| 患者ID | 〇 | 〇 | |
| ゲノム情報 | 〇 | 〇 | |
| 容貌 | 〇 | 〇 | |
| 虹彩 | 〇 | 〇 | |
| 声紋パターン | 〇 | 〇 | |
| 歩行パターン | 〇 | 〇 | |
| 静脈 | 〇 | 〇 | |
| 指紋・掌紋 | 〇 | 〇 | |
| 心身の機能の障害 | 〇 | 〇 | |
| 健康診断等結果 | 〇 | 〇 | |
| 心身改善のための指導・診療・調剤 | 〇 | 〇 |
Q14:本学が入手する試料・情報の管理はどのように行えばよいでしょうか。
A14:・研究責任者の元で原則10年間保管してください。
・個人情報を含む情報は、原則ネットワークから切り離されたHDD等に保存して鍵のかかる場所に保管ください。もしHDD等への保管が難しい場合には、本学の「Box利用ガイドライン」を遵守し、東工大ポータル上の「Box(※個人領域)」への保管をお願いします。(商用クラウドサービスの利用は不可)
・収集された試料・情報に個人情報が含まれている場合には、特別な理由がない限り匿名に加工することを推奨しています。記録のために一時的に録音・録画したファイルは、反訳(書き起こしたもの)して内容をインタビューした人に確認してもらいファイルを削除することを推奨しています。
Q15:インタビューで録音した音声ファイルを個人が特定できない状態にする方法を教えてください。
A15:音声自体が個人情報なので、一部加工しただけでは個人が特定できない状態にはなりません。加工方法として以下ご参考ください。
・発言内の「名前など個人が特定できる情報」を削除した上で、インタビュー音声のピッチやトーンを変更する
・発言内の「名前など個人が特定できる情報」を削除した上で、インタビュー音声を反訳(書き起こし)し、音声ファイルを削除する
(加工が出来ていない例)
・発言内の「名前など個人が特定できる情報」を削除する →音声そのものが個人情報です。
Q16:今回の研究で研究対象者から取得した試料・情報について、いずれ何らかの研究のために用いたり、他の研究機関に提供したりする可能性がある場合は、何か手続きは必要ですか。
A16:今回の申請書に可能性がある旨を記載した上で、実際に可能性が具体化した時点で再度倫理審査を受ける必要があります。これを行えば、その将来の研究実施や、政府や学術機関への提供時には再度同意を取得する必要はありません。一方で、ご記載が無い場合や、一般企業などに提供したりする際には、再度研究対象者に連絡を取って同意を取得してから、二次利用する必要がありますのでご留意ください。
Q17:研究対象者に謝礼・交通費等を支払う場合、どのようにしたらよいですか。
A17:・申請方法や金額設定にあたっては「倫理審査の申請」ページ>3. 申請・申出 <申請者(教員のみ)>「申請前の留意事項>「研究対象者に謝金を支払う場合」をご参照ください。
・研究への協力はボランティアであるという原則を踏まえ、「時給」ではなく1時間当たりの「謝礼」としてください。
・現金やギフトカードなど複数の方法で支払う可能性がある場合は申請書の謝礼の支払方法でも複数項目にチェックしてください。
Q18:大学(研究企画課)加入の傷害保険の手続きについて教えてください。
A18:申請書で「本学(研究企画課)加入の傷害保険」を「利用する」にチェックの上ご提出ください。学長許可後、実験実施1週間前までに「【事務局提出用】実験予定・実績表」に日次で実験予定人数を記入し、事務局にご提出ください。なお、実験実施中だけでなく実験場所への移動の間の事故等も補償されますが、途中で実験場所以外に立ち寄った場合は保険の適用外になります。
倫理審査不要申出を行った研究は、当該傷害保険を利用できません。
Q19:共同研究や受託研究など、多機関が関与する場合の申請はどのようにすればいいですか。
A19:受託研究の場合は受託研究契約書の写しを添付してください。
共同研究の場合は、研究の概要に相手先との関係(研究の分担体制や試料・情報のやり取りの有無)を記載し、「共同研究機関の有・無」欄にて有にチェックの上、共同研究契約書もしくは科研費交付申請書の写しなど、相手方および合意された研究期間がわかるものを添付してください。これらは共同研究等承諾書(様式12)でも代用できます。また、相手方の倫理審査の実施状況にチェックし、既に倫理審査済みの場合や申請中の場合は、相手方の倫理審査資料一式や審査結果通知書(承認書)の写しも添付してください。
多機関共同研究については、「倫理審査の申請」ページ> 4.多機関一括審査(本学が分担)<申請者(教員のみ)>をご参照ください。
Q20:研究計画の内容が特定の企業または団体と関係がある場合、記載する必要がありますか。また、どこに相談すればよいでしょうか。
A20:資金や設備・試薬等の提供の有無や兼業の状況など、研究者と相手方企業の関係性を申請書に記載してください。また、倫理審査申請と並行して、別途利益相反マネジメント理工学系審査委員会(産学共創機構 法務室)のチェックを必ず受けてください。
Q21:業務の一部を委託する場合はどのような手続きが必要でしょうか。
A21:申請書に委託先名称、委託する業務内容および監査方法をご記載の上、契約書類や規約の写しを添付してください。
Q22:新規(変更)申請書、報告書を作成しようとしたところ、作成ボタンが見あたらないのですが、どうしたらよいでしょうか。
A22:2023年12月1日の規則改正に沿って、2024年3月末にシステム改修が行われ、システム上の申請者権限が教員(常勤、特任、特命)に限定されました。申請者権限のある教員から申請や報告をお願いいたします。閲覧者(システム上申請権限が付与されていない方)向けに下書き用ファイルや様式集を用意していますので、「提出書類」ページ>「申請(新規・変更)の提出書類・報告書様式等/審査不要申出の使用様式」をご活用ください。
Q23:変更申請をしようとしたところ、すでに研究期間が切れてしまっていることに気づきました。どうしたらよいでしょうか。
A23:研究期間が切れている場合には、システム上変更申請の作成が出来ませんので、ただちに終了報告を提出してください。なお、研究の継続を希望される場合には、新規申請として再申請をお願いいたします。再申請の経緯を備考欄へ記載願いただきますと迅速審査とさせていただきます。
Q24:研究期間について教えてください。申請できるのは最長何年でしょうか?
A24:本学では、申請の際の研究期間はシステム上では最長5年としております。5年を超える場合には、終了前に延長変更申請をお願いいたします。
Q25:16歳未満の未成年を研究対象者へ含める研究を計画しています、倫理審査申請は必要でしょうか。
A25:16歳未満の未成年を研究対象者とする場合は倫理審査申請が必要です。ただし、16歳未満の未成年であっても、授業時間外の自由参加型の科学実験ワークショップでのアンケート調査など特別な配慮を要しない場合は除きます。その場合は倫理審査不要申出をご提出ください。(本人の自由意思で参加できる、参加/参加拒否を選択した場合でも不利益を被ることが無い 成績に影響しない等)